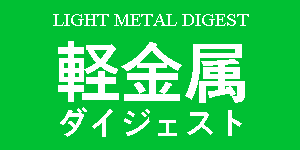
このサイトは、本誌の定期購読契約者のみが利用できるメンバー専用ページです。
 |
NO.1507(2000年10月23日号)
|
RSワタナベ
マグネホイールの販売順調
一般市販車向け浸透が牽引
レーシングサービスワタナベが販売するマグネシウムホイールの売行きが順調だ。レーシング用での高い実績をテコに一般市販車向けにも徐々に需要が増えている。
ホイールメーカーのレーシングサービスワタナベ(横浜市鶴見区元宮、渡辺俊之社長)が販売するマグネシウム合金製ホイールの需要が着実に増加している。同社はマグネシウムホイールで1ピース鋳造製品と1ピース鍛造製品を品揃えしており、今年の販売見込みは両製品合わせて7,000~8,000本程度と、本格参入した5年前に比べてほぼ10倍の規模に達する勢い。燃費効率の向上や加速性の改善など、マグネホイール装着によるメリットに対する評価が高まっていることに加え、製品の信頼性アップや不良率の低下による販売価格引き下げが需要拡大につながっている。従来のレース用にとどまらず、アフター市場を通じた一般市販車への装着が増えており、同社では来年の販売目標を1万5,000本に置いている。VIAマークも鍛造製品で4点、鋳造製品で2点取得済みで、全サイズでの取得を目指している。
同社は1Pマグネ鍛造ホイールの生産をロシアの大手メーカーに委託、3万㌧の“超ド級”鍛造プレスで製造している。同工場は原料の合金マグネシウムを大手製錬メーカーのソリカムスクから調達、生産能力はアルミニウムホイールと合わせて年間5万本。ロシアでは鍛造から切削加工まで行い、オフセット、PCD、塗装・メッキなどはレーシングサービスワタナベの水戸工場(西茨城郡友部町)及び協力会社で行なっている。水戸工場では6台の鋳造機でアルミホイールを生産。1P鋳造マグネホイールの生産は2台の鋳造機で行なっており、生産能力は年間7,200本。
同社の1P鍛造マグネホイールの年間販売量は昨年の1,000本に対して今年は1,500本の予想。一方、1P鋳造ホイールの販売量は昨年の5,000本に対して今年は6,000本を見込んでいる。
同社のマグネホイールは「軽四輪車向けに14インチサイズが好調など、販売量の約2割が一般市販車向けで最近の需要拡大の牽引役になっている」(渡辺俊之社長)。「ホイールをアルミからマグネに交換するだけで燃費効率が5%アップするのに加え、加速・減速性能、ステアリングレスポンス、ブレーキ性能などが向上する。21世紀にはマグネホイールが主流になる」と期待しており、「サーキットでの実績をセールスポイントに一般市販車向け拡大を積極的に狙っていく」(渡辺社長)という。来年の販売目標1万5,000本の内訳は、1P鍛造ホイールが9,000本、1P鋳造ホイールが6,000本となっている。
富山合金がシュレッダー設備
立山合の鋳造移管で効率改善
三協アルミグループのアルミビレット鋳造専業会社である富山合金(富山県新湊市、沖田敏雄社長)はシュレッダー設備を導入、10月6日に竣工式を行なった。三協アルミ、立山アルミ両社は企業の枠を越えた生産効率化対応の一環として、グループ内の鋳造部門の集約化を進めており、今年1月には立山合金工業が行っている鋳造事業の第1段階の移管を実施した。
今回のシュレッダー設備導入は、これまでの処理方法と比較してよりコストの安いスクラップ処理方法の確立を目指したもの。鋳造部門の集約化に伴い、三協・立山アルミ両グループ発生のアルミ形材の加工屑が富山合金に集約され、原材料の一つである加工屑の割合が大幅に増加、構内運搬効率や溶解炉への挿入効率が低下、特に溶解炉での加工ロスが大きくなっていた。新設した設備により、アルミ形材加工屑を細かく砕き、嵩比重を増加し、溶解炉に挿入できるアルミ加工屑を大幅に増加することができるという。
シュレッダー設備は富士車輌製で、能力は7.5㌧/時・2,200㌧/月。さらに、付帯設備として破砕品コンテナ(バック)搬送設備、集塵設備や、60㌧トラックスケールを導入した。総投資額は3億5,000万円。設備設計に当たっては、省力化・省人化の工夫を施した。
三協アルミグループは環境問題に取組み、ISO14001の認証取得とその実践を目指しているが、今回の設備の利用により、将来、三協アルミグループのアルミニウム建築用廃材のリサイクル推進に寄与できる体制が整ったとしている。
45周年記念特別例会開催
アルミ表面処理技術部会
(社)アルミニウム表面処理技術部会(和田健二代表幹事)は今年で創立45周年を迎えることを記念して、11月22日午後1時30分から日本出版クラブ会館(東京都新宿区袋町)において、「特別例会・祝賀会」を開催する。内容は次の通り。①特別講演「陽極酸化皮膜構造の高規則化とその応用」(都立大学大学院・益田秀樹)②講演「Al表面処理電子顕微鏡写真集の活用法」(部会長・三田郁夫、無機材質研究所・和田健二)③記念祝賀会(午後4時半~6時半)。
参加費(会誌代、祝賀会費含む)は普通会員、特定会員、電顕写真提供者、幹事が3,000円、普通会員4,000円、一般7,000円。問合せ・申込はAl部会45周年記念実行委員会まで(電話03-3252-3286、FAX03-3252-3288)。
昭和電工と昭和アルミ
来年7月1日に対等合併
技術を融合、先端市場で優位に
昭和電工と昭和アルミニウムは3日、2000年7月1日付けで対等合併すると発表した。存続会社は昭和電工。昭和アルミのアルミ加工技術と昭和電工の無機・有機化学技術を融合、最先端アルミ製品のグローバル市場で優位に立つことが統合の目的だ。
合併方式は対等合併で、昭和電工1株につき、昭和アルミ株1株を割り当てる。合併後の新「昭和電工」は資本金1,104億51百万円(合併による増加分4,992百万円)、総資産約6,800億円(同1,200億円)、売上高5,000億円(同1,400億円)となる。従業員数は約6,000名(同2,500名)。決算期は12月末。
また、社長には昭和電工の大橋光夫社長が就任し、昭和アルミの小島巖社長は代表取締役副社長の予定。両社の取締役は合計35名(昭和電工19名、昭和アルミ16名)だが、執行役員制を導入して削減する考え。合併の細目については両社で合併準備委員会(委員長・松原博昭和電工常務、山崎全昭和アルミ常務)を組織し、今後詰める予定。昭和電工の子会社でアルミ鋳造・鍛造素材会社のショウティックも新「昭和電工」に統合する方針である。
今回の昭和電工グループのアルミ事業の大合同は、アルミ事業をグループ最大のコア事業と位置付け、その強化・拡大が狙い。昭和アルミが製造・販売する電解コンデンサー箔、感光ドラム部品、カーエアコン用熱交換器、冷蔵庫用パネル、アルミ缶などは技術的に世界トップレベルにあるが、合併を機に昭和電工が蓄積する無機・有機化学、その他の技術をアルミと融合し、成長産業のエレクトロニクスや自動車、情報通信などの先端グローバル分野で技術的優位性を確立する。両社が世界各地に保有する生産・販売拠点を有効活用し、国際的視点からも業容の拡大を図る。
また、両社の本社・国内販売拠点の統合、スタッフを中心とする約250名の人員削減、人材の有効活用などを実施し、最大限のコスト削減を追求する。これらの措置により合併3年後に30億円から40億円のコストダウンが見込まれるという。同日、記者会見した両社社長は次のように語った。
【大橋光夫昭和電工社長】 当社グループは「チータ・プロジェクト」と銘打った中期計画を実施に移したが、その中でアルミ事業は連結売上高2,300億円、総売上の35%を占める重要戦略事業の柱のひとつである。アルミは今後のハイテク産業向け材料として極めて重要な成長素材であることから、両社の経営資源を完全に統合し、強化・育成することがベストの選択だと判断した。
昭和電工がぬるま湯につかったような社風といわれるのに対し、関西系の昭和アルミはどちらかというと商売にガメツいところがある。今回の統合で両社のよいところのシナジー効果も期待できる。私は若い頃昭和アルミにも、スカイアルミにも出向した経験があり、アルミには特別の思い入れがある。統合がどちらの社員とっても公平になるように配慮するのも私の役目だ。
【小島巖昭和アルミ社長】 これからのエレクトロニクスや自動車など先端産業に求められるハイテクアルミ材料は、色々な技術がコンバイン・融合されて完成される。たとえばリチウムイオン電池やポリマー電池の材料はアルミとポリマーの複合素材であるし、アルミ缶も化学系コーティングが欠かせない。ハードディスク・アルミ磁気ディスクも同様だ。今回の統合で新「昭和電工」のアルミ部門は世界的な技術競争を勝ち抜ける体制になると思う。
東エク、バス停市場本格参入
必要な機能を全てユニット化
東洋エクステリア(杉本英則社長)はバスストップシェルター「タウンステージBS1型」を新発売した。路線バスは、交通渋滞の解消、交通事故の防止、二酸化炭素の削減など自動車が直面している様々な問題を解消する交通機関として見直されているが、従来は通路用シェルターなどで対応しているケースが多かった。東洋エクステリアは業界として初めて、路線バスのバスストップに必要な機能を全て取り揃え、部材をユニット化した専用シェルターを開発、同市場に本格的に参入した。初年度売上げ目標は1億円。
柱・屋根、サイン、ポール、屋根材、照明、ベンチ、FIXパネル、貼り紙防止シートなどで構成され、現場に合わせて自由に組合せることが可能。街並みを考慮したシンプルなデザインで、本体色は3色。ネジやボルトなどを極力露出させない取り付けも実現している。
現場の状況や予算などに応じて、ポールタイプとシェルタータイプの2種類あり、写真の製品で価格は113万9,000円(ガラス、照明器具は別途)。
8月の新設住宅着工3.8%減
新設マンションもマイナスに
建設省が発表した8月の新設住宅着工戸数は10万3,554戸、前年同月比3.8%減と4ヵ月連続でのマイナスとなった。資金別では民間が7.6%増となったものの、公的資金は18.1%減であった。
利用関係別に見ると、持家が3万9,056戸、同4.3%減と7ヵ月連続の落ち込み。貸家も3万5,090戸、同8.1%減で7ヵ月連続で前年同月を下回った。
さらに、これまで好調を続け、住宅着工の下支えしてきた分譲住宅も2万8,351戸、同2.7%増と14ヵ月連続で前年同月を上回ったものの、伸び率は大幅に鈍化。とくに新設マンションは1万7,860戸、同0.4%減と14ヵ月ぶりにマイナスに転じた。新設マンションの地域別内訳は、首都圏9,992戸(前年同月比3.7%減)、中部圏1,099戸(同17.4%増)、近畿圏3,582戸(同9.2%減)、その他地域3,187戸(同19.1%増)。
キャンバス生地可動式テラス
「気象鳥」、トステムが新発売
トステム(飛田英一社長)はキャンバス生地を採用した可動式テラスの新商品「気象鳥(きしょうちょう)」と屋外スクリーン「ほの香」を開発、全国で新発売した。
住宅の1階テラス部分に設置する従来型のアルミテラスは固定式タイプが中心で、主用途は雨除け。冬場にはもっと日差しを屋内に採り入れたいとか、洗濯物を干す時以外は屋根がない開放的な空間にしたいという要望が高まっている。
トステムの可動式テラスは、夏は強い直射日光をカット、室内でのエアコンの効率が良くなり、涼しく快適に過ごすことができる。反対に日差しの低い冬はキャンバスをスクロールして開けておくことで、室内に十分光を採り入れることができるため、冬の日中の室内を明るくし暖かく過ごすことができるなど、四季に応じた省エネ機能を持つ。価格は写真の商品で30万8,500円。
富山軽金属、富山合金、日軽金新潟
今年度TPM優秀賞を受賞
本多金属・恵那は第二類で
日本プラントメンテナンス協会はこのほど、TPM優秀事業所の受賞者を決めた。アルミ業界からは第一類優秀賞に富山軽金属、富山合金、日本軽金属・新潟工場の3社が、第二類優秀賞は本多金属・恵那工場が受賞した。
同賞は、設備管理の近代化や設備管理技術の開発を促進し、企業の体質強化を図るため、1964年に同協会が制定した。今回は①特別賞に10社12事業所②継続第一類優秀賞に21社28事業所③第一類優秀賞に73社104事業所④継続第二類優秀賞に2社2事業所⑤第二類優秀賞に24社25事業所-がそれぞれ受賞した。同協会は11月9日、横浜市・パシフィコ横浜で表彰式を行なう。アルミ関連企業の受賞理由は次の通り。
累計ロス削減額は30億円
【富山軽金属工業】 「全員参加でパワーアップ。C(コスト)D(納期)Q(品質)を達成しよう」 1997年12月にTPMを長期的な課題達成の経営戦略の位置付けとして導入。
重点課題としてオペレーターによる自主保全活動の「人と設備の体質改善」と平行して、「パワーアップCDQ」をメインテーマに掲げ、ロス構造分析からロスを定量的(金額)に把握し、設備・人・原材料の改善を実施。
その結果、累計ロス削減金額は2000年7月時点で29億56百万円となった。また、納期達成度指数は1.5倍に改善、着色色調不良指数は新技術の開発によりゼロ達成工場もあった。
ビレット不良率1/3に低下
【富山合金】 「全員参加で、国際価格に挑戦」1998年3月にTPMパートⅡとして、毎年10%づつ3年間のコスト削減達成をメインテーマとする「トリプルテン作戦」をキックオフさせた。
活動内容は徹底的なロスの発掘と改善であり、①原材料の購入から製品出荷までの物流ロスの排除②生産工程の省人化の達成、効率生産方式の追求、原単位ロスの削減-を実施した。
この結果、不況による減産下での固定費アップのなか、計画比70%の達成率となり、国際価格と競合すべく目標レベルに着実に近付いてきた。同時に故障・チョコ停、ビレット不良率が三分の一になるなどの成果も得た。
工場ラインの黒字化達成
【日本軽金属・新潟工場】 「全員参加のTMで故障ゼロ・不良ゼロ・災害ゼロをめざし、設備の総合効率化と原価低減を図るTPM活動を通じて、全員の意識改革を行なおう」。1997年10月にキックオフ。アルミ押出形材市場は需要不振、販売価格の低迷、高品質要求の強まりという三重苦の厳しい環境にあったが、一連のTPM活動を通じて、工場ラインで黒字化の達成という画期的な成果を得た。
なお、日本軽金属では過去に延べ5工場・製造所が同賞を受賞、今回の新潟工場は6工場目となる。
生産性が25%もアップ
【本多金属工業・恵那工場】 「生き生きニュー本多・21世紀工場をめざして=NH-21」 大競争時代・企業格差の時代を迎え、顧客本位のものづくりの中で生き残れる体質づくりのため、1997年3月にTPM活動を導入。「NH-21」はSpeed、Simple、Standard、Strategyの4Sを行動指針とし、大型設備・装置中心職場と、人中心職場の特徴を生かした自主保全活動を推進。さらにモデル製品を選定し、スルーコストの削減活動を展開した。
その結果、生産性25%アップ、故障1/10、ロス削減金額7億円、モデル製品の総原価12%低減などの成果を得た。また、女性3名を含む機械保全技能士58名が誕生するなど学ぶ・チャレンジするという意識も向上した。
YKK黒部事業所内に建設
ファスニング機械の専用工場
YKK(吉田忠裕社長)は同社黒部事業所内に工機事業本部専用機械事業部組立工場を建設、このほど竣工式を行った。YKKグループは国内外でファスニング事業と建材事業を二本の柱として事業展開しており、工機事業本部はこれら事業向けの製造設備、金型、システムなどの開発、製造を担当している。今回完成した工場はファスニング製品用生産機械の中核工場。受注から開発、試作、組立、出荷までの一貫生産を行い、初年度3,000台の製造・出荷を計画している。
工場建屋は鉄骨3階建てで、延床面積は2万7,200㎡。設備投資額は28億円。商品開発から三次元CAD/CAM、構造解析・流動解析、NCデータ加工までのプロセスを高速大容量通信ネットワークで実現して開発リードタイムを短縮するなど、IT武装された最新鋭の工場となっている。さらに、既設の工場との景観に配慮し、労働環境、省エネルギー、環境アセスメントも考慮した。
27日にトステム財団研究会
「中古住宅の活性化に向けて」
トステム建材産業振興財団は10月27日、新丸コンファレンススクエア(千代田区丸の内新丸ビル)において、「第20回住宅・建材産業長期展望研究会」を開催する。“中古住宅の活性化に向けて”がテーマで、内容は次の通り。
▽あいさつ:トステム財団▽消費者(居住者)から見た住まいの検査について:消費生活アドバイザー小倉恢子氏▽米国における中古住宅検査の実際:カリフォルニア州在住、インスペクターK.オマリー氏▽質疑応答。参加費は無料で、申込は同財団まで(電話03-5626-1008、FAX03-5626-1033)。締切は13日。
トステムの人事異動
(10月1日付)▽取締役副社長兼執行役員副社長建材総本部長兼生産本部長、菊池光男▽専務執行役員住宅建材本部長兼住宅建材本部販売統轄部長、竹野恭二▽執行役員岡山統轄工場長、若林隆▽特需・直需本部直需統轄部FC部長、佐藤憲男▽特需・直需本部特需統轄部特需第五部長、冨澤曠彦▽販売統轄部総合化推進部長、吉田博敏▽店装建材事業部店装建材販促部長、杉田福男▽店装建材事業部店装商品開発部長、晝間幸雄▽業革
統轄部営業教育部長、菊地弘行▽特需・直需本部直需全国営業部中部支店長、長谷川金吾▽北海道統轄支店直需担当支店長、高橋秋三▽関東統轄支店西千葉支店長、山岸崇彦▽北関東統轄支店茨城支店長、新井智秀▽北関東統轄支店長群馬支店長、吉田聡。
図・表・写真は本誌でご覧ください。

|