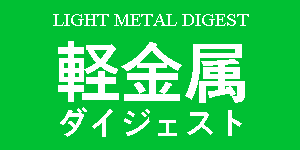
このサイトは、本誌の定期購読契約者のみが利用できるメンバー専用ページです。
 |
NO.1509(2000年11月6日号)
|
日本タイプライター
マグネの表面処理工場が稼働
前処理から塗装まで一貫対応
日本タイプライターが新設したマグネシウムの表面処理設備が本格稼働入りした。ノンクロムの化成処理から粉体塗装までの一貫ラインで、予想を上回る引き合い・受注を受けており、2002年に30億円の売上げを狙う。
キヤノングループの日本タイプライターが建設を進めていたマグネシウム合金成形品専用の表面処理設備が完成、10月から本格稼働入りした。化成処理から粉体塗装までの一貫ラインで、既にMD、携帯電話、ノートパソコン、カメラなどのケースの表面処理を手懸けているが、引き合いも多く寄せられるなど予想を上回る立ち上がりとなっている。2002年度にはマグネシウムの表面処理で30億円の売上げ達成を目指す。
マグネシウム専用ラインは同社の岩井工場(茨城県岩井市)にある表面処理工場STC(Surface Technical Center)の既存建屋内にに新設したもの。前処理工程は既存のめっき設備を一部改造して対応、環境に配慮して自社開発技術によるノンクロムの化成処理を採用した。さらに粉体塗装設備1ライン(メサック製)を設けた。総投資額は5億円弱。A4ファイルサイズのノートパソコンケース換算で月40万台の能力を持つが、40インチサイズの壁掛けテレビのフレーム、自動車部品など異形部品にも対応可能。浴の管理などはコンピュータ制御で行なっており、将来的に前処理から塗装までの完全自動化一貫ラインを構築する方針。
現在はユーザーの要望に応じて、一次塗装のみ粉体で行い、二次塗装(仕上げ塗装)は溶剤塗料で対応するケースもあるが、塗料メーカーと共同でカラーバリエーションの充実を進めており、行く行くはすべて粉体塗装で対応する体制を作り上げる考え。さらに、塗膜品質をアップさせるために、ダイキャストやチクソモールディングなどの成形メーカーとの協力関係も強めて行く。
これまでにMD、携帯電話、パソコンケースに加え、キヤノンの高級一眼レフ「EOS-1V」ボディなどの表面処理を受注しているが、さらに有力な引き合いも多く寄せられている。2002年度のマグネシウム表面処理部門の売上げは、当初予定していた20億円を上回る30億円規模となる見込みにあり、来年後半をメドにさらにもう1ラインの増設も検討する模様である。
同社の表面処理部門はキヤノンや自社製品への表面処理加工を主体にしてきたが、外部の需要を取り込んで事業拡大を図る狙いから、92年に約90億円を投じて最新鋭の表面処理工場であるSTCを建設した。環境対策に万全を期しており、12億円を投じて国内で最も厳しい"琵琶湖基準"をクリアする排水処理施設を建設、ISO14001の認証も取得している。
同社は、マグネシウム合金の表面処理分野への新規参入に加え、既存の無電解ニッケルめっきやUV塗装の強化も進めており、99年12月期で約47億円の表面処理事業売上げを2002年度には70億円を上回る規模に引き上げる。
古河電、業績大幅上方修正
光関連製品の売上げ絶好調
古河電工は今期業績見通しを大幅上方修正した。単独中間経常利益は150億円(前年同期比17.9 倍)と今年5月発表の45億円から105億円の大幅増額となる。売上高は2,590億円(同6.9%増)と予想に比べ40億円の上方修正にとどまるものの、WDM(波長分割多重伝送)関連製品をはじめとした光関連製品など新商品の売上げ構成比アップと固定費を含むコストダウンが寄与する。当期純利益予想は160億円(前年同期は2億4,700万円の欠損)。カナダ持株会社JDSUの株式売却益の一部475億円を受取配当金として特別利益に計上する一方、特損300億円を計上する。
通期見通しも売上高5,480億円(前期比8.6%増)、経常利益350億円(同4.7倍)、当期純利益420億円(同2.9倍)と大幅経常増益予想。WDM関連製品のさらなる売上げ拡大に加え、非鉄圧延品も好調なことによる。
また、連結の修正通期見通しは、売上高8,000億円(前期比14.9%増)、経常利益600億円(同158.9%増)、当期純利益1,510億円(同4.3倍)。連結範囲拡大により非鉄圧延品部門の売上げが増加。また、中間期でJDSU社株式の売却に伴い、有価証券売却益を約2,000億円を特別利益として計上する。
神鋼、半導体事業から撤退
KTMの株式を米社に売却
神戸製鋼は18日、同社が保有するKTMセミコン ダクター(兵庫県西脇市平野町302−2、資本金421億円、高橋出雲男社長、従業員約900名)の全株式を米国マイクロン・テクノロジーに売却すると発表した。これによりKTMはマイクロン社の100%子会社となる。事業譲渡は2001年3月末で、マイクロン社は譲渡完了時に125百万ドル(135億円)を神戸製鋼に支払うとともに、神戸製鋼が融資および保証を行なっていたKTMの借入債務約500億円を全額引き継ぐ。この結果、神戸製鋼の連結総資産は2000年9月末比810億円、外部負債残高は630 億円それぞれ減少する。
KTMは神戸製鋼75%、マイクロン社25%の出資比率で設立された半導体DRAMの製造販売会社。1996年から1998年に業績が悪化し、神鋼グループの赤字体質の原因の一つとなっていた。
今回の撤退について水越浩士社長は次のように語った。
「当社は中期経営計画に沿って、選択と集中の観点からコア事業に絞り込む事業再構築を進めている。その点、半導体事業は当社のコア事業とはいえず、KTMはマイクロン社に経営移管したほうがベストと判断した。また、半導体事業は当面300億円を超す投資が必要で、財務面からも売却したほうがよい。この事業の収支は約100億円の損失だが、出向者の人件費などを勘案するととんとんではないか」
なお、神戸製鋼所は18日、当中間期業績予想の最終損益を520億円の損失に修正した。KTMセミコンダクターの売却に伴う特別損失が210億円発生するため、赤字幅が期初予想から120億円拡大する。
三菱アルミの下期販売計画
板前年比2%増、押出1%減
三菱アルミニウム(福地淳二社長)は今年度上期の販売実績と下期計画を発表した。板の上期販売実績は1万2,696㌧/月、前年度上期比1.8%増、同下期比8.1%増。猛暑を追い風に缶材が計画を上回る伸びを達成、自動車熱交向けも順調。今年度下期販売は前年同期比2.1%増の予想。缶材、国内一般向けは横ばいながら、IT関連の好調継続に加え、穏やかな景気回復と輸出の多少の伸びを見込んでいる。
一方、押出の今年度上期販売実績は2,059㌧/月、前年上期比10.1%増、同下期比4.1%減。トラック関連は微減だったが、二輪車・乗用車、機械、自動車熱交向けが堅調に推移。ビル向けは物件が集中し、計画を上回ったが、その他一般材は減少。今年度下期は、全般的に引き続き堅調な受注を見込んでいる。二輪車・乗用車、機械、自動車熱交向けが上期比横ばいないし若干増を予想。トラック関連は横ばい、ビル向けやその他向けは上期比減少の計画となっている。
箔の上期販売実績は前年上期比9.0%増、同下期比1.5%減。今年度下期は前年同期比0.8%増の予想。コンデンサをはじめとしたIT関連市場が好調なうえ、軟包装向け、日用品、容器も需要期を迎えることもあり堅調に推移。輸出は東南アジア市場の回復で環境は好転しているが、国内向けの繁忙から上期比横ばいの計画。
ニュースレター「アルミと健康」
「アルミニウムと健康」連絡協議会(山口寿敬議長、日本アルミニウム協会内、電話03-3538-0221)はこのほど、ニュースレター「アルミニウムと健康」第5号を作成した。
トップページには、7月に自治医科大学大宮医療センター神経内科の植木彰教授を招いて行なった講演会(テーマ「アルツハイマー病と食事栄養因子」)の内容を紹介。さらに、昭和女子大学の福島正子助教授の講演「日本人のアルミニウム摂取状況と最近の研究」を2回に分けて連載する。
なお、同協議会は、今年5月に開催した第2回「アルミニウムと健康」フォーラムの講演録も発行している。経口摂取されたアルミニウムの体内での挙動やアルツハイマー病に関する最新の研究動向に関する講演と来場者からの質問に講師が分かりやすく答えたパネルディスカッションの内容も掲載している。
金秀アルミ工業
デミング・実施賞を受賞
TQM活動で業績大幅改善
金秀アルミ工業(沖縄県中頭郡西原町、山里秀夫社長)は17日、2000年度におけるデミング賞を受賞した。アルミ関連企業の受賞はアルミ二次合金・アルミダイカストのアーレスティに次ぐ。
デミング賞は日本科学技術連盟(井田勝久理事長)が主催する表彰制度で、全社的品質管理(TQM)活動の発展や普及に功績のあった経営者、およびTQM活動を通じて目覚ましい業績改善を実現した企業に贈られる。2000年度は本賞に前田建設の前田又兵衛会長が選出されたほか、業績を向上させた企業に贈られる実施賞を金秀アルミ工業、サンデン物流(群馬県東村)、サンワテック(群馬県新田町)、ジーシー(東京都板橋区)の4社が受賞した。表彰式は11月14日、東京・大手町の経団連会館で行なわれる。
金秀アルミ工業は1971年に沖縄軽金属として設立、1988年に金秀グループのアルミ関連企業7社を統合して現社名とした沖縄県で唯一のアルミ押出形材サッシ企業。バブル崩壊後、アルミ形材・アルミサッシの需要不振、設備過剰、価格低迷、表面処理を中心とする設備の老朽化などの対応に苦慮したため、抜本的な経営改善策として、1996年から「TQM導入」を軸とする5ヵ年中期経営計画を策定、実施に入った。
その結果、顧客の信頼性を高める市場クレームゼロの品質保証体制を基本に、開発から生産までの短納期化と少量多品種生産への俊敏な対応が進展。国内最南端の地方企業ながら、大手企業に先行してアルミ関連ではいち早くISO−9001、ISO−14000を取得するなど企業体質・業績の改善・改 革、顧客満足度の向上、人材育成などが大幅に進み、これが高く評価された。中期計画のキーワードは「脱島小(沖縄弁でシマーグワー)」、「脱サッシ」、「脱中小企業」。
山里社長によると、今後アルミ形材では「多品種・小ロット、短納期」を旗印に県外の需要開拓と、リフォームや太陽光発電システム、介護保険住宅などの新規事業開拓を進め、年商100億円以 上の中堅企業を目指すという。
軽金属押出開発
ISO9002を取得
軽金属押出開発(中増建太郎社長)はこのほど、9月19日付けでISO9002を取得したと発表した。認証機関はデット・ノルスケ・ベリタス(DNV)。認証範囲は「アルミ及びアルミ合金の押出製品の製造」。認証番号はISO9002:1994。
同社は国内で唯一のアルミ大型押出材の供給者としての認識に立って品質システムを確立し、顧客のニーズと信頼に応える品質を提供するため、1999年10月1日に品質ISOの取得活動をキックオフ。1年内の短期間で認証取得にこぎつけた。これ により①顧客の信頼が高まり、企業イメージの向上が図られる②品質の安定向上により歩留まり向上、不良低減が促進し、コストダウンにつながる③社員の品質に対する意識が向上し、全社的なモラルアップが図られる−等のメリットがあるという。
日軽プロダクツの新型踏み台
グッドデザイン賞を受賞
日軽金グループの家庭日用品販売会社、日軽プロダクツ(東京都江東区、朝倉司朗社長)が10月から発売した新型踏み台「ステーブルステップST2」が今年度グッドデザイン中小企業庁長官特別賞」を受賞した。審査は(財)日本産業デザイン振興会。
従来、家庭用踏み台は実用一辺倒であったが、使用時の事故を防ぐための天板・踏み桟の大型化と収納性の向上という相反する条件を満たすとともに、草花を置くなどインテリアグッズとしても使用可能なようにデザイン性も高めた。
踏み桟と天板(335×260㎜)を広くするとともに、ノンスリップ性と外観滑り止め防止のため独自の波形形状を採用。今年6月に改訂された新安全規格(SG規格)に適合する安全性を確保した。使用時サイズは490×680×800㎜で、収納時には厚さが48㎜となる。素材の88%をアルミが占めるため重量は4.2㎏と軽量。価格は1万円で、年間6,000台の販売が目標。
なお、日軽プロダクツは98年に組立て式アルミ収納ラックでグッドデザイン中小企業庁長官賞、99年に組立て式アルミCDラックでグッドデザイン賞を受賞している。
抵抗シーム溶接に大きな反響
愛知産業がデモ機展示会開催
愛知産業(井上裕之社長)は10月5〜6日、同社館林工場内で「抵抗シーム溶接機技術開放展示実演会」を開催、来場者は約550名に及んだ。10種類以上の機械で10種類以上の材料の溶接を実演、古川一敏営業部長が1機種づつ用途や特徴について説明、来場者から活発な質問が飛ぶなど大きな関心が寄せられた。
同社は約20年前からシーム溶接機の国内生産を開始し、これまでの実績は300台を超えている。電気容量は従来の約10分の1なうえ、高品質の溶接、軽量コンパクト化、高速溶接接合を実現しており、10種類以上の抵抗シーム溶接機を開発製造している。今回の展示会開催は、こうした豊富な経験と技術を広く一般に公開して欲しいというユーザーからの要望に応えたもの。
住団連の「住宅景況感調査」
7〜9月期は再び大幅悪化に
住宅生産団体連合会(山口信夫会長)はこのほど、住宅メーカー19社の経営者を対象に10月に実施した「住宅景況感調査」の結果を発表した。
今年度第2四半期(7〜9月)実績の景況判断指数は受注戸数がマイナス26ポイント、受注金額がマイナス24ポイントと前年同期に比べて大幅に悪化した。総受注戸数の景況感指数は99年1〜3月のプラス55ポイントをピークに下降に転じ、今年1〜3月はマイナス29ポイントに落ち込んだ。4〜6月は0ポイントまで回復したものの、再び大きく下落した。
調査企業19社のうち受注実績が前年同期に比べて「10%以上良かった」と「5%程度良い」と回答した企業は3社にとどまり、反対に、「マイナス10%程度・以上悪い」と「マイナス5%程度悪い」と回答した企業が11社にのぼっている。依然として厳しい雇用・所得環境を理由として挙げ、各社とも危機感を強めている。
続く、第3四半期見通しの景況判断指数は、受注戸数がプラス24ポイント、受注金額もプラス26%とプラスを予測している。回答企業19社のうち、10社が「5%・10%以上よくなる」、7社が「変わらず」と予測している。公庫金利先高感、ローン減税効果、自社の営業努力による受注拡大に期待感がある一方、住宅取得マインドの冷え込みや展示場来場者の減少傾向が懸念材料。
なお、今年度の新設住宅着工戸数の予測は19社平均で118万8,000戸(平成11年度実績122万6,207戸)。最高が121万戸、最低が115万戸で、中心の118〜120万戸を予測しているのが14社と最も多くなっている。利用関係別の予測平均では、持家44万5,000戸(同47万5,632戸)、分譲住宅31万2,000戸(同31万2,110戸)、賃貸住宅42万戸(同42万6,000戸)。
立山アルミの人事異動
(10月16日付)<役員の委嘱>▽事業統轄本部長兼環境担当及び人事担当、取締役副社長・要明英雄▽市場開発推進部長兼ビル建材事業部長、専務取締役・沖英郎▽事業統轄副本部長兼住宅建材事業部長兼エクテリア事業部長、同・篠原清▽商業施設事業部長兼サイン事業部長兼東洋テルミー担当、常務・網谷英三▽生産統轄本部長兼環境対策部長、同・川崎清司▽事業統轄本部購買担当、同・熊崎哲男▽事業統轄本部予算管理兼商業施設事業担当、取締役・保多尚宏。
訃報
中安道治氏(なかやす・みちはる=宇部興産相談役、元代表取締役会長、元日本マグネシウム協会会長)10月22日午前3時25分、心不全のため死去、72歳。自宅は山口県宇部市恩田町2-3-1、電話0836-21-0950)。24日自宅での通夜に続き、25日教念寺(宇部市上宇部)において中安家と宇部興産の合同葬を行なった。喪主は妻の滋子さん。葬儀委員長は常見和正宇部興産社長。
中安道治氏は、昭和3年1月4日生れ。28年大阪理工科大学理工学部応用化学科卒業後、宇部興産入社。平成4年代表取締役会長、7年取締役相談役、9年相談役等に就任。日本マグネシウム協会の設立・活動に尽力し、平成3年6月〜9年6月会長、現在まで名誉会長の職にあった。8年6月国際マグネシウム協会功労賞、10年6月日本マグネシウム協会特別功労賞を受賞。
欧州の自動車アルミ化・・・・・自動車委員会調査
欧州ではアルミ化が常識に
大型化対応で熱処理不要の材料
日本アルミニウム協会・自動車委員会(川瀬寛委員長)は9月19〜27日、「欧州における自動車のアルミ化調査チーム(チーム長=小宮清美スカイアルミニウム生産管理部次長)」を派遣、このほどその調査結果の概要を発表した。
同調査団は「アルミニウム2000」とIAAに参加するとともに、アウディ社や欧州アルコア社を訪問。小宮チーム長は「欧州では自動車のアルミ化は常識。生産技術は完成しており、今後さらに普及するかどうかは、材料メーカーがいかにアルミを安く提供するかにかかっている」と総括した。以下は報告のポイント。
1.「アルミニウム2000」
①展示会
ハイドロ、アルコア、コーラスなどのアルミメーカーと、ホンセルなどの押出や鋳物メーカー、その他熱処理や加工の装置メーカーが出展。アルミスペースフレームでは、アルコアがフェラーリ360モデルのホワイトボディ、ホンセルがアウディA8のホワイトボディ、ハイドロがBMWZ8のカットモデルをそれぞれ展示。その他、自動車の部品として展示されていたのは表のとおり。
②講演
自動車関連の講演は6件行なわれ、①ドイツが2006年初めまでに、リユースリカバリーを含み85%のリサイクル目標を設定②アルミはリサイクルに有利③アルミが将来大きく伸びるかどうかは「リサイクルのアイデア」が重要・・など、環境・リサイクル関連が印象に残った。
さらに、スペスフレーム構造の小型車を量産しているアウディは初代のA8とA2を比較しながら技術・加工法などの"進化の過程"を説明、今後の方向性も示した。例えば、溶接はA8のスポット+MIG溶接に対し、A2ではレーザー+MIG溶接に変化。さらに、鋳物(主として真空ダイキャスト)による薄肉・大型・多機能一体部材を提案しているほか、部品の大型化や接合の増加に伴って要求される精度アップのため、ハイドロフォームを利用、寸法精度±0.2㎜を達成。また、接合点数の削減によるコストダウンをめざして、ドアのインナーは一体成形によっている。
ボルボはアルミニウムの積極的な利用による重量軽減と環境への配慮を重視しており、CO2排出 量は現状の210㌘/㎞から2008年には140㌘/㎞を狙う。材料としては、インナー:5182、アウター:6016あるいは6111。
2.IAAモーターショー
42ヵ国・1,246社の出展。前回(1996年)のようなアルミスペースフレーム構造の提案は少なかった。展示内容のポイントは、①大型トラック、トレーラー:日本のようなバントラックは少なく、アルミ形材を使用した幌カーゴが主流②小型トラック、バンはオールアルミ製荷台が多い③バス:パネルはプラスチックやアルミを使用④特殊車両:足場板や平面部にはアルミ縞板が当然のように使用されており、また液体・粉体輸送用のタンク・バルク車には軽量化のためアルミが使用⑤部品:アルミ製エアタンクや燃料タンクはドラムとエンドパネルをMIGで接合・・など。
3.企業訪問
①アウディ社
ネッカースウルム工場でアウディA2の車体組みたてを見学。A2の部品点数は225部品で、構成は鋳物24.8%、押出17.6%、板57.6%。94年発売のA8は部品数334部品で、鋳物21.7%、押出22.9%、板55.4%。A2のスペースフレーム重量は153㎏(A8は249㎏)。
A2の生産量は300台/日(3班3交代・5日/週)。自動化率は80〜90%。接合はMIG溶接:20㍍、レーザー溶接:30㍍、セルフピアシングリベット:1800点(A8はMIG:70㍍、セルフピアッシングリベット1800点、スポット;500点、クリンチ:178点)。接合時の歩留まり向上のために押出材の加工品の精度を±0.2㎜に設定、それを達成するのにハイドロフォーム技術を応用。アルミホワイトボディは組み立て後、剛性アップのT6熱処理を205℃×30分で行なっている。
②アルコア・ヨーロッパ社
A8の生産を目的に6年前に設立。従業員300人。主要設備は、バキュームダイキャスト(バキュラル)750㌧2台、1500㌧2台、4000㌧1台(A2のBピラーを成形)、マシニングセンター10台(鋳造用4台、押出材用6台)、熱処理炉など。押出材はホンセルやアルコアの関係会社から購入し、ベンダー、ストレッチベンダー、ハイドロフォーミングの加工を行なっている。
生産品目はA8の各種部品、A2のBピラー、フェラーリモデナのAピラー、ベンツSクラスクーペのBピラーなど。A8については、部品約90点を50〜70台分/日をジャストインタイムでアウディ(ネッカースウルム工場)へ納入。
バキュームダイカストでは、最小板厚1.6㎜まで製造可能で、サイクルタイムは54〜90秒/個。ベンツワゴンバックドアについては、米国研究機関も含めて開発中で、日本のカーメーカーと共同開発しているものがある。
現在使用している熱処理合金はSiを含むC448(AlSi9Mg)だが、コストダウン及び寸法精度を向上させるために、熱処理無しの鋳造材料を開発中で、C446(AlMg3Mn)を提案している。ただ、80℃以上の使用では耐食性が低下するという。
図・表・写真は本誌でご覧ください。

|