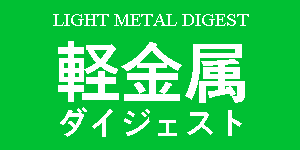
このサイトは、本誌の定期購読契約者のみが利用できるメンバー専用ページです。
 |
NO.1516(2000年12月25日号)
|
本誌アンケート調査
2000年度の売上高ランキング
4割強が増収確保、2桁増22社
本誌恒例の「アルミ企業の売上高ランキング」では対象企業200社のうち増収を確保した企業は89社、うち2桁の伸び率は22社という結果が明らかになった。
本誌はこのほど、恒例の「アルミ企業の売上高ランキング」をまとめた。アルミ業界に比較的関連の深い代表的な企業200社をピックアップし、1999年10月から2000年9月までの決算期の売上高についてアンケート及び取材調査したもの。
それによると2000年度の売上高は200社合計で5兆7,944億4,500万円で、前年度の5兆9,054億5,600万円を1.1%下回った。
200社のうち、「増収ないし横ばいを」を記録 したのは89社、うち2桁の増収は22社に上った。反対に2桁の減収となった企業は29社を数えている。
因に、増収率ランキングではニチメン金属販売(旧・高愛)は売上高が倍増したが、ニチメン鉄鋼販売との合併によるもの。これを除いた上位10社は東日本鍛造55.9%、埼玉プレス鍛造33.0%、恵那アルマイト32.3%、軽金属押出開発23.4%、サンリット工業22.5%、日商岩井メタルプロダクツ(現・日商岩井アルコニックス)22.2%、日広アルマイト21.9%、植田アルマイト19.4%、ニューウォールシステム18.7%、金秀アルミ工業16.5%−−となっている。
対象企業の若干の入れ替えや変則決算、合併・事業再構築などの影響により厳密な比較は困難なものの、昨年の本誌調査による1999年度の売上高200社合計の減収幅が10.1%、「増収ないし横ばい」が25社、「2桁以上の増収」が9社、「2桁の減収」が103社−−であったのに比べると、少なくとも売上面では企業収益が回復軌道に乗りつつあることがうかがえる。
無論、各企業は不採算部門からの撤退など経営資源の「選択と集中」による利益率重視の経営を強めているなかで売上高だけを云々する時代ではない。また、“アルミ関連”とはいっても、業態は大きく異なり、アルミ以外にもさまざまな事業、素材・製品へ展開している企業も多く、これらを一緒くたに比較すること自体無理がある。さらに、決算期も大きなズレがある。
この「ランキング」は非上場企業などの売上げ規模や、あくまでも広い意味での“アルミ関連業界”でそれぞれの企業のどの辺りに位置しているかを知る手がかりにすぎない。
東洋製罐中間、アルミ缶微増
PET31%増、増勢止まらず
東洋製罐の2000年9月中間決算における飲料容器売上高は1,706億2,800万円で、前年同期比2.9%増となった。内訳は金属缶が1,114億4,100万円(前年同期比4.7%減)、PETボトルが591億8,600万円(同20.3%増)で、明暗を分けた。
出荷量では金属缶が3億2,583.3万ケース、同1.5%減になったのに対し、PETボトルは27億8,700万本、同31.2%増と好調に伸びた。
金属缶の内訳はアルミ缶が構成比32%で約1億426.7万ケース、前年同期比1.3%増。スチール缶が68%で2億2,156.6万ケース、同3.3%の減少。発泡酒を中心にビール用が好調だった。スチール缶はコーヒーを除く清涼飲料がPETボトルに食われた。
当上期は、お茶類、炭酸飲料、健康ドリンクを主体に500mlの小型PETボトルが大幅に伸長、900ml以上の大型ボトルもお茶類、健康ドリンク、ミネラルウォーターなどの家庭内消費が拡大し、小型・大型とも生産が間に合わない状況が続いた。一方金属缶では、アルミ缶が発泡酒を含むビール用は堅調だったが、炭酸飲料、健康ドリンク、紅茶など清涼飲料向けが大きく減少、金属缶からPETボトルへの移行が顕著に進んだ。
通期の飲料容器売上げは金属缶2,000億円(前期比5%減)、PETボトル1,000億円(同13%増)、合計3,000億円(同0.2%増)の予想。金属缶出荷量は4億9,300万ケース(同6%減)、PETボトル出荷量は46億本(同28%増)の予想。
マグネ部品の長期需要予測
日本マグネシウム協会策定へ
日本マグネシウム協会はワーキンググループ「マグネシウムの戦略技術会議」を設けて、自動車向けマグネシウム部品の長期需要予測を含む報告書を策定中で、2001年3月までにまとめて公表する予定。その一環として、世界の自動車向けマグネシウム部品の需要量は2000年の9万8,000t、2005年18万3,000t、2010年29万7,000tと予測している。
なお、日本における現在の自動車分野におけるマグネシウム部品の使用実績は、ステアリングホイール2,400t、キーロックシリンダー570t、シリンダーヘッドカバー410t、シートフレーム120t、オイルパン、ブラケット他20t−−の合計3,520tとしている。
ホンダエンジ高精度曲げ加工
機振協・通産大臣賞を受賞
機械振興協会はこのほど、2000年度同協会賞の受賞9件を決めた。特に機械工業の進展に優れた功績のあった企業を対象とする通産大臣賞には、ホンダエンジニアリング(埼玉県狭山市)の「自動車用アルミニウム骨格部材高精度曲げ加工システムの開発」が選ばれた。
本田技研が1999年秋に発表、35km/lの超低燃費を達成した「インサイト」の軽量車体「アルミニウムハイブリッドボディ」は、従来高コストであったアルミボディを軽量化・高剛性・衝突安全性性能の確立を前提とした上で低コスト化した、生産性に優れる新構造。
ホンダエンジニアリングは車体構造上最も重要な骨格部材であるアルミ押出形材について、高精度化とコスト競争力を両立した三次元曲げと捻り加工を行なう従来にないシステムを構築し、量産化を実現した。同社は曲げ加工の高度化を実現するため、1)高精度・高剛性曲げ加工機
2)高精度曲げ・捻り加工の最適化を実現する加工軸構成
3)加工中の固定型・可動型間距離の制御 4)高機能曲げ加工用CAMによる曲げ、捻り加工精度誤差の最小化――などを開発、寸法精度、材料歩留まりを飛躍的に向上させた。
これにより、製品設計から加工までのリードタイムの短縮、設計変更に対するフレキシビリティなど少量生産化が可能となり、従来法に比べ30%以上のコスト低減と、精度バラツキを5分の1以下に抑制できた。
上期のアルミ建材出荷額
4478億円、2.4%減に
通産省窯業建材統計に基づいて日本サッシ協会がまとめた2000年度上期のアルミ建材の生産・出荷統計(確報値)によると、アルミ建材合計の生産量は26万870t、前年同期比0.3%増、出荷量は27万2,031t、同0.5%増となった。ただ、出荷金額(生産者販売金額)は4,478億2,700万円、同2.4%減と引き続きマイナスを記録した。
品目別では、サッシは生産が17万1,522t(前年同期比1.1%減)、出荷が18万1,214t(同0.6%減)で、出荷金額は同3.4%減の2,918億3,400万円。このうち、住宅用サッシは出荷量が11万631t(同0.8%増)、出荷金額が1,618億2,100万円(同0.7%増)。t当り単価は146万円と前年度上期比ほぼ横ばいであった。
一方、ビル用サッシの出荷量は7万583t(同2.6%減)、出荷金額は8.2%減の1,300億1,300万円。t当り単価は184万円と前年同期の195万円から5.6%下落した。
YKKR&Dセンターが環境ISO
滑川・東北に次ぎ3番目
YKKAP(吉田忠裕社長)のYKKR&Dセンター(東京都墨田区)は12月1日付けで国際標準化機構の環境マネージメントシステム規格ISO14001の認証を取得した。YKKAPの環境ISOの取得は1998年12月の滑川事業所(富山県滑川市)、2000年6月の東北事業所(宮城県古川市)に続くもの。
YKKR&Dセンターは1993年6月の竣工以来、建材事業における商品開発、商品設計の中心的な役割を担い、多くの環境配慮型商品の開発設計を担当してきた。YKKグループでは今後、営業部門についても認証取得に向けた準備を行ない、環境ISOの認証取得を全社に拡大する予定。
日本坩堝の技術顧問に就任
東工大名誉教授の神尾彰彦氏
工業炉大手の日本坩堝(岡田民雄社長)は12月1日付けで、わが国の非鉄金属溶解鋳造・金属材料の研究では第一人者といわれる東京工業大学の神尾彰彦名誉教授を「技術顧問」に招聘した。
神尾教授は去る3月末、東京工業大学を定年退職し、同大名誉教授に就任したばかり。日本鋳造工学会の前会長を務め、日本金属学会、日本マグネシウム協会の理事を歴任するなど、著名な非鉄金属研究者として知られる。1999年5月には軽金属学会会長に就任している。
アルミ労協一時金5.9万円増
最高はトステムの77.9万円
全国アルミ産業労働組合協議会(吉田守会長、48単組3万8,000名)の2000年年末一時金交渉は12月8日までにほとんどの単組が終結、妥結額単純平均は41万9,080円、1.62ヵ月分となつた。前年同期の35万9,963円、1.40ヵ月分と比べると金額で5万9,117円、月数で0.22ヵ月分のアップ。
これを加重平均でみると50万8,276円、1.91ヵ月分となり、前年同期比では金額で6万1,405円、月数で0.21ヵ月分の増加。アルミ関連企業の一時金はアルミ需要の長期的な低迷で、ここ数年前年実績を下回る不振が続いたが、ようやく底を脱した。12月13〜14日に開催する中央幹事会で総括する。
妥結最高額はトステムの77万9,034円、2.93ヵ月分(前年同期75万5,793円、2.936ヵ月分)。前年ゼロに終わった不二サッシ、三協アルミ、協立アルミ、富山軽金属、ショートクなども金額は低いものの有額解決となった。ただ、トステムを除いて業績の回復が遅れているサッシ関連は、全般に低額妥結となっており、業種間格差、企業間格差は一段と拡大した。
大政日本テクノ社長が博士号
振動攪拌技術の工業化研究で
日本テクノ(東京・大田区久が原)の大政龍晋社長はこのほど、母校の名古屋工業大学工学部応用化学科から工学博士号を授与された。審査の対象となった学位論文は「振動攪拌技術の工業化に関する研究」。
振動攪拌技術は全く新しい攪拌方法ではないが、従来行われていた振動攪拌技術は実験室レベルないしは特定の工程を対象にしたもの。大政社長は、一定の周波数領域で液が三次元流動することを見出して以来、振動攪拌方法を従来の回転式羽根付攪拌方式に代る汎用性の高い高性能な攪拌技術として確立するとともに、その技術を用いてさまざまな工業的応用分野を開発した。
この新たな振動攪拌技術を応用することで、既存の攪拌技術では満足な結果を得られなかったり、技術的に不可能であったプロセスを可能にした。
図・表・写真は本誌でご覧ください。

|